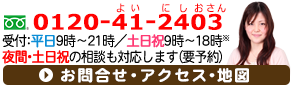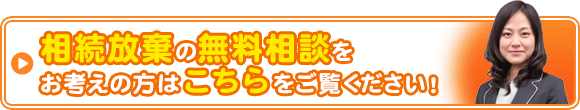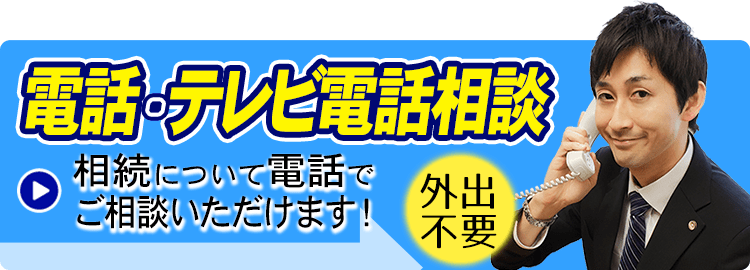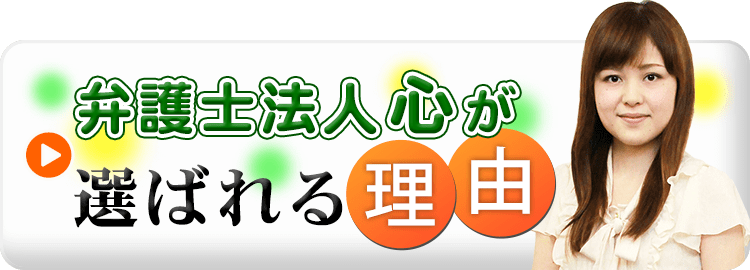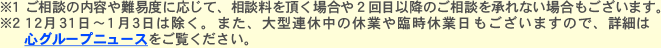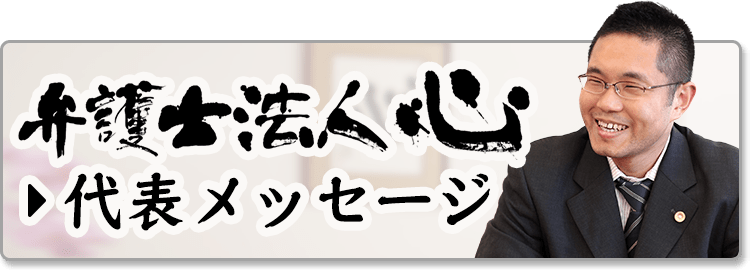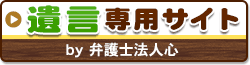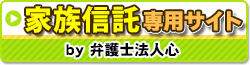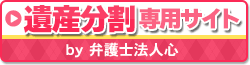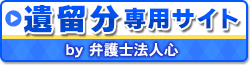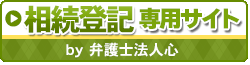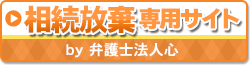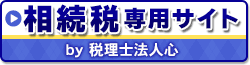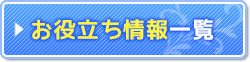生前贈与を受けていた場合でも相続放棄はできるのか
1 生前贈与を受けたとしても法律上は相続放棄は可能
生前贈与を受けていたとしても、法律上は、相続放棄を行うことはできます。
相続放棄は、被相続人が亡くなってから3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出することにより、認められます。
つまり、このような手続を行えば、生前贈与を受けた相続人であっても、相続放棄を行うことができることとなるのです。
また、被相続人が亡くなった後に、相続財産を処分した場合には、相続放棄はできないこととなっています。
生前贈与を受けた財産は、贈与の時点ですでに相続人に権利が移っており、相続財産には含まれないものとなりますので、生前贈与を受けたことは、相続財産の処分に該当するものではありません。
この点でも、生前贈与を受けたことは、相続放棄の障害にはならないこととなります。
なお、生前贈与された財産は、贈与の時点で所有権が相続人に移っていますので、相続放棄したとしても、基本的には返還する必要はありません。
ただし、後述の詐害行為取消の主張がなされた場合には、生前贈与された財産を返還しなければならなくなることもあります。
以上から、生前贈与を受けたとしても、法律上は、相続放棄を行うことができることとなるのです。
2 生前贈与を受けたことが相続放棄の障害になることはないか
法律上、相続放棄は可能だとしても、生前贈与を受けたことが相続放棄の障害となるようなことがあるのであれば、相続放棄を避けなければならないことも出てくると思います。
生前贈与を受けたことにより発生する障害として、以下の2点を説明したいと思います。
① 詐害行為取消の主張がなされる可能性がある
先述のとおり、相続放棄したとしても、基本的には生前贈与された財産を返還する必要はありません。
ただ、被相続人が債務を有している場合については、注意が必要です。
債務を返済することができなくなってしまっている場合(つまり、債務超過になってしまっている場合)、債権者にとっては、生前贈与がなされなければ、債務の返済を受けることができたのにと思うところかと思います。
このため、債権者を害することを認識してなされた贈与については、債権者の側から、生前贈与をなかったことにするとの主張を行うことが認められています。
これを詐害行為取消権と言います。
詐害行為取消の主張が認められた場合には、相続人は、生前贈与された財産を返還しなければならなくなってしまいます。
詐害行為取消権は、債権者が贈与をなされたことを知ってから5年間、または贈与がなされてから20年間は主張することができます。
もちろん、詐害行為取消は、債権者が主張すれば生前贈与された財産を返還しなければならなくなる制度ですので、債権者が贈与の事実を知らなかったり、詐害行為取消の主張をしてこなかったりして場合には、生前贈与された財産を返還する必要はないこととなります。
以上から、被相続人が債務超過になってしまっている場合で、生前贈与がなされてから20年が経過していない場合については、債権者から詐害行為取消の主張がなされ、生前贈与された財産は返還しなければならなくなる可能性があり得ることは、注意する必要があります。
② 遺留分侵害請求がなされる可能性がある
生前贈与の結果、相続財産がほとんど残っていない状態や債務超過の状態になってしまう場合には、他の相続人から、遺留分侵害額請求の主張がなされる可能性があります。
遺留分侵害額請求の対象になるのは、相続財産だけではなく、被相続人が亡くなる前の10年間に生前贈与された財産も含まれます。
このため、生前贈与がなされたことを理由として、他の相続人から遺留分侵害額請求がなされ、一定の金銭を支払わなければならなくなる可能性があります。
さらに、相続放棄をしてしまうと、他の相続人が主張できる個別的遺留分が増えてしまいます。
というのも、他の相続人が請求できる個別的遺留分は、総体的遺留分に他の相続人が有している相続分を乗じることにより決まることとなりますが、相続放棄を行うと、他の相続人が有している相続分が増えてしまうこととなるからです。
このため、相続放棄をしたことにより、他の相続人に遺留分として支払わなければならない金額が増えてしまうこととなるのです。
以上から、生前贈与の結果、相続財産がほとんど残っていない状態や債務超過の状態になってしまう場合で、生前贈与がなされてから10年が経過していない場合については、他の相続人から遺留分侵害額請求の主張がなされ、遺留分に相当する金銭を支払わなければならなくなる可能性があります。
遺留分について相談する弁護士の選び方 お役立ち情報トップへ戻る