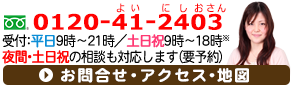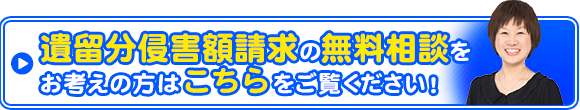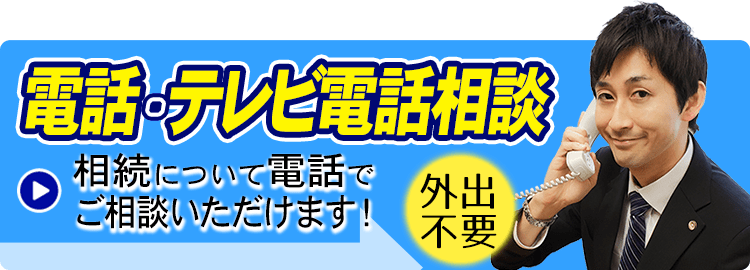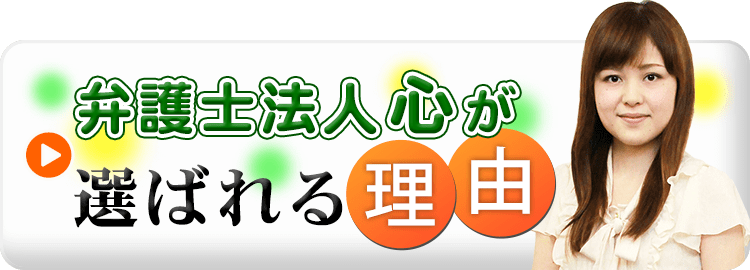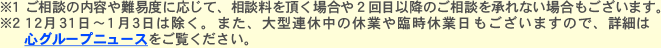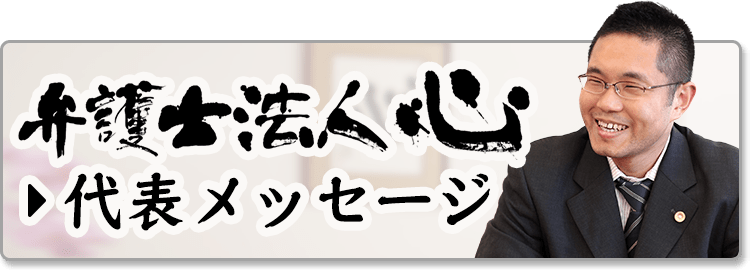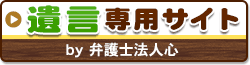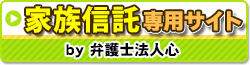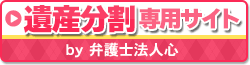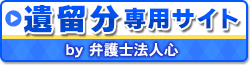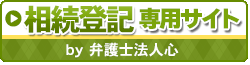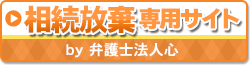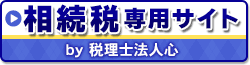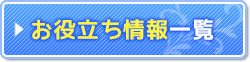遺留分について相談する弁護士の選び方
1 遺留分を正確に計算できる弁護士
遺留分で勝負を分けるポイントは、いくつかあります。
これらのポイントに分けて、遺留分について相談する弁護士の選び方を説明したいと思います。
まずは、遺留分について正確に計算できる弁護士であることです。
このことを述べると、遺留分を正確に計算できるのは、当たり前のことではないかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
確かに単純な計算でしたら、遺留分の計算を間違える人はいないでしょう。
しかし、実際には、遺留分の計算の落とし穴にはまったり、遺留分の計算がかなり複雑になる事情が存在したりすることで、弁護士でも、遺留分の計算を間違ってしまうということがあり得るのです。
たとえば、相続人が配偶者と兄弟姉妹であり、相続財産のすべてを、被相続人が生前に懇意にしていた第三者に遺贈するとの遺言が残されていた場合、配偶者の遺留分はいくらになるのでしょうか?
遺留分は相続分の半分であるという考えを持ってしまっている人は、配偶者の相続分4分の3の半分である、8分の3と誤った計算をしてしまうでしょう。
正確には、総体的遺留分2分の1が存在し、これを主張できるのは配偶者のみとなりますので、配偶者の遺留分は2分の1になります。
他にも、債務超過にはならないまでも、多額の相続債務が存在する場合、相続人に対する複数の多額の生前贈与が存在する場合、相続開始後に遺留分の放棄がなされている場合、遺留分義務者が複数存在する場合等については、遺留分の計算は複雑になってきます。
こうした案件でも、正確な知識に基づき、正しく遺留分を計算することができる弁護士に相談すべきでしょう。
2 相続財産の調査、相続財産の察知ができる弁護士
遺留分については、財産を十分に調べることができる能力が要求されます。
特定の人にすべての財産を相続させる遺言や、遺贈する遺言が残っていたとします。
この場合、財産を引き継ぐこととされた人は、他の相続人の協力を得ることなく、ほとんどの財産の払戻や名義変更の手続を行うことができます。
このため、他の相続人は、どのような財産について払戻や名義変更の手続がなされたか、手続の過程では知る機会がないこととなります。
このような場面で、財産を引き継ぐこととされた人が、どのような財産が存在するかについて、情報を隠してしまおうとすれば、どのようなことが起こるのでしょうか?
たとえば、どこにどのような不動産が存在するのか、どの銀行にいくらの預金が存在するのか等の情報を隠してしまったら、どうなるのでしょうか?
他の相続人は、被相続人の財産の情報が隠されてしまい、いくらの相続財産が存在するかを確認できなければ、事実上、遺留分を請求することはできなくなってしまいます。
また、中途半端な調査をしてしまうことにより、相続財産の調査漏れが発生してしまうおそれも生じてきます。
多額の相続財産の調査が漏れてしまうと、その相続財産を除外して遺留分を請求してしまうこととなり、本来請求できる金額の請求ができなくなってしまうこととなります。
もちろん、相手方が相続財産についての情報をすべて任意に開示してくれれば、それに越したことはないですが、案件によっては、任意の情報開示が期待できないことがあります。
このように相続財産についての情報が隠されてしまうおそれがある中で、十分な遺留分の請求を行うためには、十分に相続財産を調査する能力が求められます。
どこにどのような問い合わせを行うことにより、相続財産の調査を網羅的に行うことができるかについて、知識、経験が要求されることとなるのです。
また、現存する断片的な情報から、相続財産の存在を察知する能力も要求されます。
たとえば、預金の出入金記録上、公社債の利息の入金があった場合には、公社債が相続財産として存在するとの推定が働きます。
相続財産について十分な情報を得るためには、こうした公社債の利息の入金といった、断片的な記載を見逃すことなく、預金の出入金記録等を精査することが要求されます。
このように、網羅的に相続財産を調査したり、相続財産の存在を察知したりすることができる弁護士に相談すべきでしょう。
3 相続財産評価についての知識を有している弁護士
遺留分では、相続財産評価を適切にできるかどうかが勝負を分けることがあります。
たとえば、相続財産に不動産が存在するとして、この不動産をいくらと評価すべきなのでしょうか?
固定資産評価額、相続税評価額等、財産評価については、全国一律の指標が存在しますが、このような指標では、財産の評価を適切にできないことがあります。
特に、不動産から賃料収入が発生している場合については、賃料収入をベースに評価額を算定する手法(収益還元方式)を加味して評価を行うことが適切であることがありますが、固定資産評価額、相続税評価額だけでは、賃料収入を織り込んだ評価を行うことはできません。
相続財産に非公開会社の株式が含まれている場合についても、同様の問題が発生します。
もちろん、弁護士は不動産鑑定士や公認会計士ではないですので、単独で不動産や非公開会社の株式の評価を行うことはできません。
正確な財産評価を行うためには、やはり、不動産鑑定士や公認会計士に依頼する必要があります。
とはいえ、相続財産調査を行ったときや相手方から情報開示を受けたときに、この財産は適切に財産評価を行うと値上がりする傾向があるかどうか、弁護士の方で勘を働かせることができれば、不動産鑑定士や公認会計士に本格的な財産評価を依頼する等、その後の方針を立てやすいと言うことができます。
また、交渉や訴訟の場面においても、このような勘を働かせることにより、ここは強気の主張を行うべきである、ここは鑑定申出を行うべきである等、当面の主張をどのように行うべきかの方針を立てやすいと言うことができます。
他にも、実態のない債務が相続債務として計上されている場合については、相続債務の評価を行うことができるかどうかが問われてくることもあります。
遺留分について相談する場合は、相続財産評価についての知識を有している弁護士に相談すべきでしょう。
相手が遺留分侵害額請求に応じてくれない場合の対処法 お役立ち情報トップへ戻る