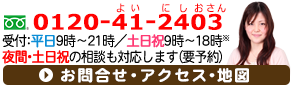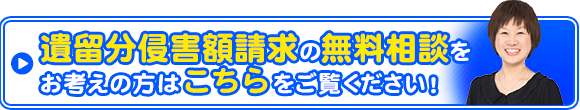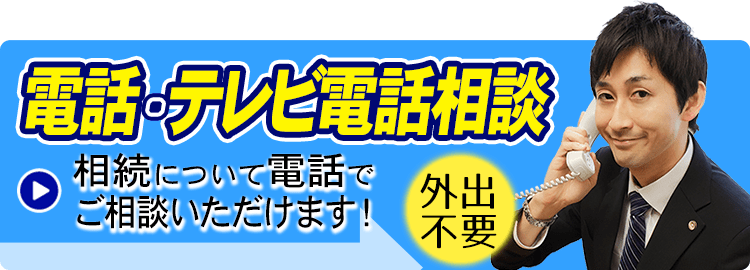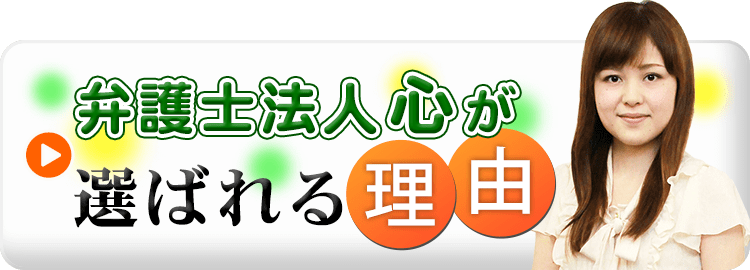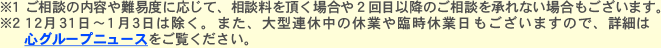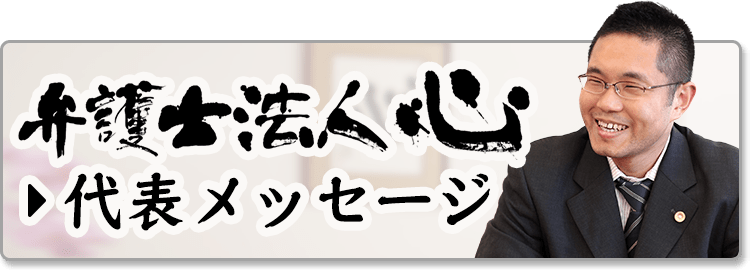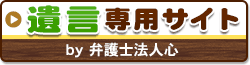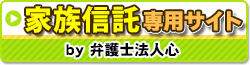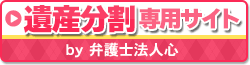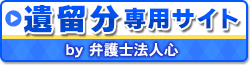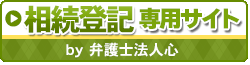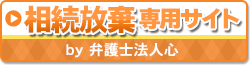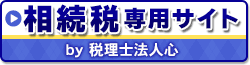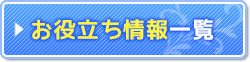相手が遺留分侵害額請求に応じてくれない場合の対処法
1 遺留分について
遺留分は、法律上認められた、相続の最低限の権利のことを言います。
ある相続人遺言によりがすべての財産を相続するものとされていたとしても、他の相続人には遺留分がありますので、すべての財産を相続するものとされた相続人に対し、遺留分侵害額請求を行うことができます。
遺留分は、基本的には、相続分の半分となりますが、生前贈与がある場合は、遺留分が増減する可能性があります。
遺留分侵害額請求を行うときは、金銭の支払を求めることができます。
このように、遺留分は、相続の最低限の権利であるにもかかわらず、相手が金銭の支払等に応じないことがあります。
このような場合は、どうすれば良いのでしょうか?
2 法的手続を利用する
相手が遺留分侵害額請求に応じない場合は、法的手続による解決を試みることとなります。
法的手続としては、家事調停手続を利用することが考えられます。
法律上は、遺留分についての争いがある場合は、まずは調停手続を用いることとされています。
家事調停手続とは、家庭裁判所に当事者が赴き、家庭裁判所の調停委員を介して、当事者同士の話し合いによる意見調整を行うことを言います。
調停手続は、家庭裁判所で行われる手続である以上、基本的には、法律論を重視して意見調整がなされますが、最終的には、当事者の合意による解決を図ることとなります。
このため、当事者間の意見対立が激しく、合意による解決が見込めない場合は、調停手続では解決できないとして、調停手続が終了することとなります。
次に、法的手続として、訴訟手続を利用することが考えられます。
訴訟手続は、地方裁判所(請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所)で行われる、いわゆる裁判のことを言います。
先述のとおり、遺留分侵害額請求については、法律上は、まずは調停手続を用いることとされていますが、話し合いによる解決がまったく見込めない場合等には、調停手続を経ずに最初から訴訟手続を用いることが認められることもあります。
訴訟手続では、当事者が法律論に基づく主張を行い、最終的には、裁判所が判決を下すこととなります。
ただ、実際には、訴訟手続の途中で、裁判所の主導のもと、当事者が話し合いを行い、合意により解決(和解)することも多いです。
相手が遺留分侵害額請求に応じない場合は、法的手続を利用すれば、法律論をベースとする解決が見込めます。
相手が払いたくないと思っていたとしても、法律論に基づいて支払う義務があると考えられる場合は、法的手続を利用して支払を求めていくことが考えられます。
遺産分割の方法とそれぞれの特長 遺留分について相談する弁護士の選び方