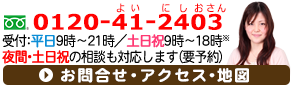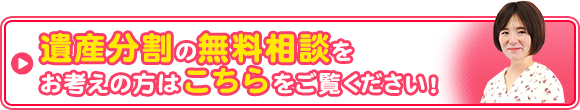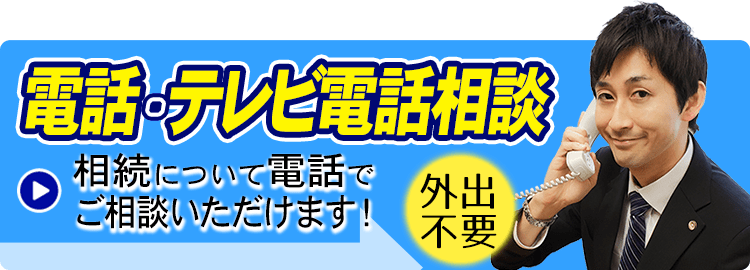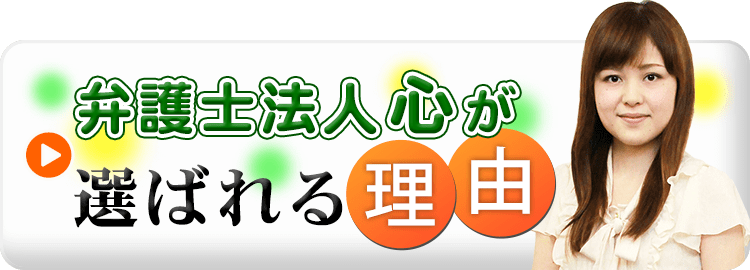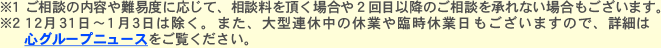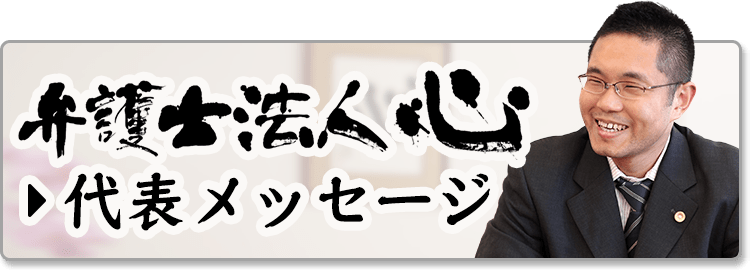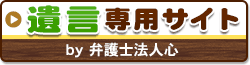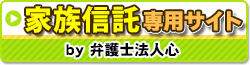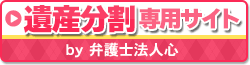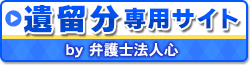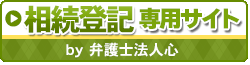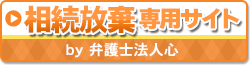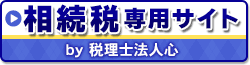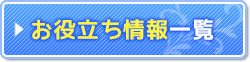遺産分割の方法とそれぞれの特長
1 遺産分割の方法
遺産分割は、被相続人が遺言を作成しており、分割方法について指定していれば、それに従うことになります(民法908条1項)。
被相続人が遺言を作成していない場合の遺産分割は、①相続人間での話し合い(遺産分割協議)によって行い、②遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停による合意がされ、③調停も不成立となった場合には遺産分割審判に移行し、家庭裁判所が分割方法を決定します。
家庭裁判所は、遺産に属する物又は権利の種類及び、性質、その他一切の事情を考慮して遺産分割を決定します。
一口に遺産分割といっても、さまざまな方法があります。
そこで、次に各遺産分割法について簡単な説明とその特長についてご説明します。
2 現物分割
現物分割とは、個々の相続財産をそのまま分ける方法です。
A、B、2人の相続人がおり、相続財産が家と預金であった場合に、Aが家、Bが預金を受け取る、というかたちです。
現物分割の特長は、合意さえ成立すればよく、特別な計算や処分を要しないため、代償分割や換価分割より簡易な点にあります。
遺産分割は、その性質上できる限り現物を相続人に受け継がせることが望ましいため、遺産分割の原則的方法といえます。
3 代償分割
代償分割とは、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させた上、他の相続人に対する債務を負担させる方法です。
先の例の家が2000万円の価値で預金が1000万円であるとすると、Aが1000万円分Bより多く取得することになるため、AがBに対し、500万円支払うことを約束する、というかたちです(A=家(2000万)-500万=1500万、B=預金(1000万)+500万円=1500万円)。
代償方法の特長は、相続人間で平等を図りつつ、相続財産を残すことができることにあります。
代償の分の資力を要しますが、建物など単純に分けられないが売りたくない財産がある場合に選択される方法です。
4 換価分割
換価分割とは、遺産を売却等で換金(換価処分)した後に、その代金を分配する方法です。
先の例でいえば、家を売って2000万円に変えて、預金と合わせて、AとBが1500万円ずつの現金を得る、というかたちです。
換価分割の特長は、相続財産を処分して得られた金銭を分ける方法ですので、代償分割とは違い、分割前に代償の資力を有しないとしても、選択可能であるという点にあります。
5 共有分割
共有分割は、遺産の一部又は全部を具体的相続分に従い共有取得する方法です。
先の例でいえば、遺産の一部である家を売らず、AとBの1/2ずつの共有として預金は半分ずつとする、というかたちです。
共有分割の特長としては、代償金を支払うこともできず、処分が困難あるいは相続人が残したいと考えている場合に選択される方法です。
ただし、共有した建物を相続後処分するなどする場合は全員の同意が必要とするなどの負担が生じるデメリットが生じます。
共有分割は選択肢というより、上の3つができない、あるいは3つの方法のいずれかでは、公平性を害する場合の帰結といえます。
信託銀行と専門家の違い 相手が遺留分侵害額請求に応じてくれない場合の対処法